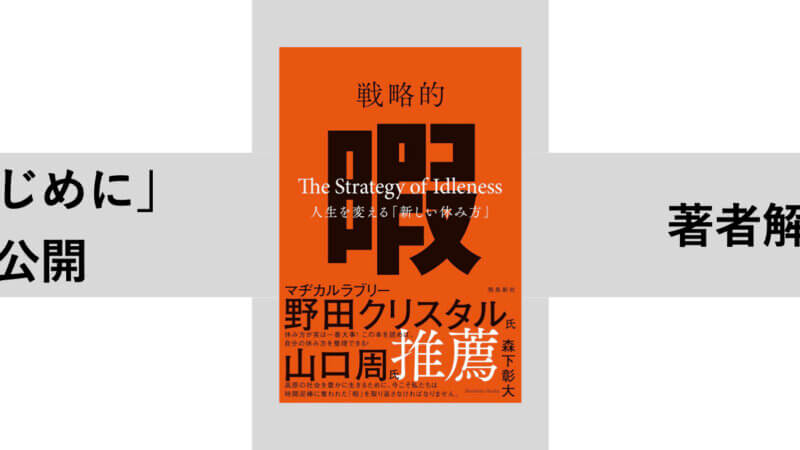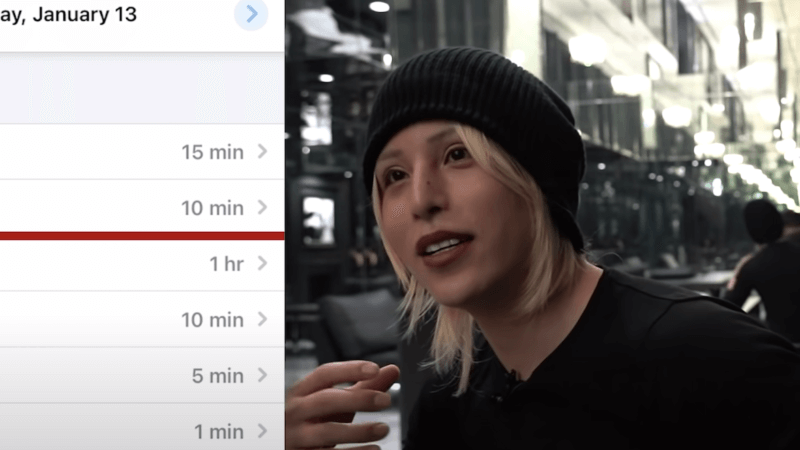目次
※本記事は書籍『戦略的暇―人生を変える「新しい休み方」―』の一部を抜粋・編集しています。
出版記念トークイベントも複数予定しております!ぜひ遊びに来てください!
▼LIVE
5/18 岐阜県大垣市 『戦略的暇』出版記念トークライブ スマホを置いて笑いにおいで!
6/28 東京渋谷 シブヤ駅前読書大学『戦略的暇』出版記念トークショー
自分の悩みはみんなの悩みだった
はじめまして。本書を手に取っていただき、ありがとうございます。森下彰大です。普段はウェブメディア「クーリエ・ジャポン」で、編集者として海外の新たな視点を日本に届ける仕事をしています。
また、コロナ禍以前より、一般社団法人日本デジタルデトックス協会(略称:DDJ、DIGITAL DETOX JAPAN)の理事としても活動しています。DDJが掲げるテーマは、デジタル技術に依存するのではなく「共存」していくこと。
これまでに、皆でスマホを使わずに過ごす野外イベントや企業向け研修、資格講座など、デジタルデトックスについて学び、楽しく体験できるプログラム作りに取り組んできました。
デジタルデトックスという言葉は長いので、今後は「DD」としましょう。DDとは、現代のデジタル疲れに対処するための「新しい休み方」のことです。
DDと聞くと、デジタル技術のすべてを否定するような考え方と捉えられることもありますが、そうではありません。
あくまで僕が提案しているのは、「休息」です。現代人にとって、スマホはもはや身体の一部みたいなものなので、身体の他の部位と同じようにスマホもお休みの時間を作ろうということです。休肝日やスポーツ選手の休息のようなもの、と考えていただければと思います。
DDの活動を始めたきっかけは、僕自身のデジタル疲れやスマホ依存でした。スマホ依存を自覚したのは、大学生のとき。特に用もないのに、暇があるとFacebookを開いている自分がいました。そこで、試しにスマホからSNSアプリを一掃したところ、いたずらにスマホを触る時間が減っただけでなく、頭がすっきりする感覚が得られたのです。
しかし大学を卒業して働き出すと、今度は仕事で否応なくデジタル漬けの状態に。昼夜を問わず連絡を取らなければならないプレッシャーもあり、体調は徐々に悪化していきました。
あるとき、夜中にスマホが振動したので何事かと手に取ったのですが、スマホには何の通知もありませんでした。幻聴のような症状が現れたことで、「このままでは本当にまずい」と感じるようになりました。
そこで会社員生活を続けながら、再びDDを実践することにしました―今度は一人でなく、皆で。
まずは友人を誘って、一泊二日のDD合宿をすることにしたのです。一斉にスマホの電源を切って、あとは食事やトレッキング、温泉や談笑を楽しむなど……。社会人になってから目の前のことにただ浸る時間がほとんどなかったことに気がつきました。
その後、DDJを立ち上げた代表理事の石田国大氏と出会いました。同じ志を持つ方との出会いに運命を感じ、共に活動することに決め、現在に至ります。
「ケイパビリティ」ではなく「キャパシティ」の問題
DDJのプログラムを開催するうちに、徐々にではありますがDDに関心を持ち、参加してくれる人が増えていきました。コロナ禍でデジタル疲れに悩む人が増え、企業や学校からもDDに関する講演依頼をいただくようにもなりました。
こうした活動の中で、僕の悩みは皆の悩みであることを確信するようになりました。
DDの体験イベントを開催していると、実に多くの発見があります。まずスマホの電源をOFFにして専用のケースに預けるのにも勇気が必要です(そもそも電源の切り方を知らない方もいらっしゃいます)。
参加者の方は、最初は手持ち無沙汰な状態。ポケットに手を伸ばし、スマホを取り出そうとして「預けていたんだった……」と苦笑いを浮かべる方も少なくありません。
それでも次第に、スマホの不在が気にならなくなります。スマホの世界のことを忘れて、アクティビティや目の前の人との対話に没頭する人が増えていきます。スマホがないことから居合わせた人たちの会話が増え、夜に焚き火を囲む頃には皆の表情が柔らかくなります。
宿泊型のイベント参加者からは、「本当によく眠れた!」「目や肩の痛みが楽になった」などの感想をいただくことも多く、短い時間であっても確実な効果があることがわかりました。
「スマホで写真撮影ができない分、目の前の風景を注意深く観察できた」「目の前のことに集中できたのが嬉しかった」といった感想もいただきました。
中には、DD体験をきっかけに自分のやりたかったことや好きなことを振り返る時間をその後の生活で作るようになり、新たなキャリアを歩み出す人もいます。
参加者の方の変容を間近で観察する中で、こう考えるようになりました。
今の私たちに足りないのは、余白ではないか。
私たちが思うように力を発揮できないのは「能力(ケイパビリティ)」ではなく、「許容量(キャパシティ)」不足が原因なのではないか、と。
スマホの充電は満タンなのに、自分の充電はできていない人がたくさんいます。それは、勿体ないこと。DDにはキャパシティを確保するだけでなく増大させる、単なる休息以上の可能性があると、数々の参加者の声や国内外の研究に触れて感じたからです。
戦略的〝暇〞が生まれるまで
僕は活動を通じて、DDは世の中に余白を作る行為なんだと気がつきました。余白、つまり、暇です。
このデジタル化した社会で一切のデジタル機器なるものから(一時的であれ)離れる時間を作るわけですから、DDをするときに私たちは〝究極の暇人〞になるわけです。
この「暇人」の状態になるからこそ、気づけること、得られるものがある。多忙な日常生活にほんの少しの暇(余白)を取り入れるだけで、英気を養い、これまで見過ごしてきたこと(たとえば、抑圧してきた自分の感情や想い)に気づき、本来の力を開花させる人は増えるでしょう。
DDの体験に来てくれる人たちは人生の転機にあることが多く、次のキャリアを模索する人や休職を余儀なくされた人も少なくありません。彼らは無意識のうちに自分が変わるための「余白」を求めていて、DDという方法に辿り着いたのかもしれません。
現代において、「暇」は何も生み出さない非効率的な存在として―「暇とは埋めるべきもの」だと―、隅に追いやられています。
しかし、暇を人間社会の中心に置き、その創り方と活かし方について考えることで、もっとたくさんの人たちが休息を得て、人生を変えるエネルギーを自ら生み出していくのではないでしょうか。
そして、その休息は忙しい現代の暮らしの中にも簡単に取り入れられます。
革命は「ベッド」から─「どう休むか」の前に「なぜ休むか」
あらかじめ断っておきたいのですが、本書は単なる「休息のためのハック本」ではありません。
過労が社会問題になっている昨今、休息にまつわる方法論が多々出回っていますが、多くは「どう休むか(How)」について説かれており、そもそも「なぜ休むか(Why)」を本質的に問うものはほぼ皆無です。
ではなぜ休むのか―この問いに答えるとするならば、それは自分の人生に、ひいては社会に 「ポジティブな変革を起こすため」です。ただ、明日も明後日も同じように考え、働き、現状維 持をするために「休む」のではありません。
自分が変わるためにも、社会が変わるためにも、たくさんのエネルギーが必要だから「休む」のです。
本書を手に取られている方の中には、行き場のない徒労感に苛さいなまれている方もいるでしょう。 仕事のパフォーマンスを上げたい方もいれば、なんとなく「今の生活を変えたい」と願う方もい るかもしれません(これまでDDイベントに参加くださった方々のように)。
まずはあれこれ考える前に「ねえ、ちょっと疲れてるんじゃない?」と自分に問いかけ、早めに暇を作ることを、そしてその暇の過ごし方を変えてみることをおすすめします。
暇をもって充足の時間を作り出すのは、勇気ある行動です。人生を変えるために本当に必要な ことから目を背け、他人の意見やネット上の情報に右往左往するだけなら、面倒な思考や勇気な んて必要ありません。しかし、満足できない人生をやり過ごすために「頑張っている」のだとし たら、逆にそれは怠慢とすら感じます。
ジョン・レノンが、〝Living is easy with eyes closed〞と歌った通り、「人生は目を閉じて生きていれば容易い」のです。皆が思考停止状態で忙殺される中、自分ひとり休むほうが勇気を求められ る。そんな時代に私たちは生きています。今こそ、その勇気を持ってほしいと思います。
私たちに必要なのは自分のための余暇を取り戻し、その余暇で培われた思考やエネルギーを個人と社会にとってより良い方向へと向けるための「戦略」です。
そして、その戦略──つまり「戦略的〝暇〞」の技法を示すのが本書の役割だと考えています。 戦略的〝暇〞を実践する人が増えれば、あなたが変わり、最終的には個人の集合体である社会 をも変える力になると、僕は信じています。
休むだけで、自分のみならず社会まで良くなっていく―。なんだか素敵な革命だと思いませんか?
そんなことが可能だと信じる人も、まだ信じられない人も、ぜひほんの少しのあいだスマホをしまい、本書を読み進めてください。
So, I start a revolution from my bed.
だから、僕はベッドから革命をはじめるのさ
―Don’t Look Back In Anger (Oasis)
▼戦略的暇―人生を変える「新しい休み方」―
【著者解説】逃げることにこそ戦略が求められる時代に
「疲弊した天才が犯した誤算」。この言葉を聞いて、思い浮かべる歴史上の人物はいるでしょうか。
ナポレオン・ボナパルト。軍事においては天才的な手腕を発揮したことで知られる英傑ですが、彼は1812年のロシア遠征において計り知れない損失を出したことは有名です。以降、フランスでの彼の評価は失墜しました。
モスクワの厳冬、ロシア軍の戦わず後退するという焦土戦術に手こずり、徐々に軍としての統率を失い、最終的には撤退を余儀なくされたこの戦い。敗因として、これまで築いた戦績が招いた過信があったこと、そして、ナポレオンが度重なる戦で疲弊していたことが指摘されています。
つまり、慎重になるべきタイミングで冷静な判断ができなかった。戦局が悪化したときに「一時撤退の決断」を下せなかったことが原因であると。
戦略において、あるいはサバイバルにおいて、「一時撤退」や「戦略的撤退」は、非常に重要であり、真っ当な判断です。
サバイバルにおいても、最初に確保すべきは「シェルター」であり、外的脅威から身を守れる環境を整えてから、エネルギー源の確保に臨むべきだとされています。
今日のビジネスの世界でも、周囲の情報だけをみて、「いまがチャンスだ」「いまはこれをやったらヤバい」と判断を下してしまいがちです。しかし、周りの情報に右往左往する前に、まず問うべきなのは「自分に充分なエネルギーがあるかどうか」ということではないでしょうか。
充分なエネルギーがない人は、そもそも「いつでもピンチ」で「いつでも劣位」の状態にあるのです。まずはこの状態を脱するべきだと思います。ですが、本書で指摘しているとおり、多くの人が疲労の状態にあるのが事実です。
僕がこれまでお会いした経営者の方々を振り返っても、優れた実績を残す方はエネルギーに溢れていました。彼らは「疲れていない」のです。逆に短絡的な判断を下したり、その場の感情に飲み込まれてしまう人は往々にして「疲れて」いることに気が付きます。
本の冒頭で、「私たちは脳腐れの時代に生きている」という指摘をしました。いま、プライベートから仕事まで、私たちは常にデジタル機器を通して情報を摂取し、脳をスピンさせ続けるという、常時接続社会に生きています。
さらに資本主義の根底には、常に効率的であるべきだ、常に頑張って働くべきだといったスティグマ(固執)があり、私たちは、有限のエネルギーをあたかも無限であるかのように燃焼させながら、「頑張って」います。
でも、そもそもなぜ頑張るのか?そもそも自分はどう生きたいのか?何のために「休む」のか?
エネルギーが枯渇するいま、自分のことに注意を傾けられる人がどんどんと減っています。外部の刺激に注意が流出してしまっているのですから無理はありません。
だからこそ、本書では「自分にエネルギーを取り戻す」こと、そしてそのエネルギーを自分の人生のために注ぐための技法を紹介しています。それが第一歩だと、デジタルデトックスの活動を通じて確信したからです。
暇にすら戦略が求められる時代。本当の意味で人がサステナブルに生き続けるために、一時脱却の時間を取らなければなりません。そしてある意味ではそんな「サボり方」は学校や企業で教えてもらえるわけではありません。
この「サボる」という言葉の語源はフランス語の「sabotage」です。もともとは「木靴で機械を叩いて壊す」という意味で、労働者の抵抗運動を示すものであり、社会変革を促すための行為でした。この言葉は、いまの日本ではかなりネガティブに捉えられています。
しかし、過労ストレス社会、環境破壊、資本主義がもたらす効率主義やナウイズム(すぐに結果を求める傾向)の跋扈…いまの社会をより良いものに変えるために、戦略的に「サボり」を取り入れて、自らに憑いた呪いを解き、エネルギーを蓄える時がやってきたのではないでしょうか。
そして、そのエネルギーをいまこそ自分の人生のために活かしていくべきではないでしょうか。
暴力的な社会運動は要りません。私たちは「立ち止まる」だけで人生を、あるいは社会までをも変えていけるのです。
もしそんなことが可能だとしたら──。